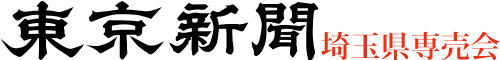<神の座の右に坐(ざ)したまふといふことのしみじみと沁(し)む裁きを終へて>は、十八年間にわたり最高裁判事を務めた入江俊郎氏の歌▼神ならぬ身で、人を裁く。その重みを、入江氏は繰り返しうたった。戦後最大の冤罪(えんざい)事件といわれた「松川事件」の審理にあたった時には、こんな歌を残している。<うづ高きこの記録はや罪なしと決めてまた繰る手ずれし記録を>▼有罪か無罪かを決めてなお、本当にそれでいいのかと証拠に向き合う。そういう謙虚さが司法にしかと根付いていれば、この「事件」はまったく違った展開になっていたのではないか。そう思わせるのが、きのう大阪高裁が再審開始を決定した一件だ▼滋賀の病院で重篤な患者が死亡した。警察は事件とみて調べ始めたが、確証は出ない。謙虚に「自然死かも」と調べることもないまま捜査を突き進め、看護助手の西山美香さんが殺人で有罪とされた▼彼女の自白はころころ変わり、本人が知るはずもなかったことまで、突然供述し始めた不自然さ。その不自然さを看過した裁判所。大阪高裁が捜査当局による「供述の誘導」の可能性を指摘し、裁判やり直しを命じたのも当然だろう▼<人が人を裁く懼(おそ)れは知らざるにあらず殺人の記録また繰る>も、入江氏の歌。そういう懼れを司法が軽んずれば、誰もが冤罪の犠牲者となりうる恐れが、不気味にふくらむだけだ。
ためしよみはお気軽にお問合せください0120-026-999営業時間 9:00~18:00 [祝日を除く平日]