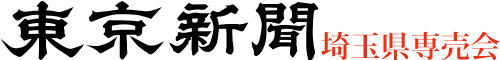映画「二十四の瞳」などの木下恵介監督は口述筆記で脚本をまとめていたようだ。ある夜、熱海の仕事場で助監督にせりふを書き取らせていたが、この助監督のもとに子どもが生まれたと連絡が入る。「ここはいいから、行ってあげなさい」▼監督はそう言ってくれるが、それでは脚本が進まない。助監督がためらっていると「いいんだ、いいんだ」。深夜で電車もなく、熱海から東京までのタクシー代は監督が支払った。助監督時代の脚本家、山田太一さんの大切な思い出である▼晴れの日。一生の間にそういう日は何日あるのだろう。入学式、成人式、結婚式、子どもの誕生…。監督に限るまい。家族であろうと赤の他人であろうとその日を祝い、守ってやりたいと考えるものだろう▼ひどい話があったものである。成人式の日、振り袖レンタル業者に大枚を払って依頼していたはずの晴れ着が届かない。連絡さえ取れぬ。ショックはいかばかりだったか。一生に一度の日が傷つけられた▼この件で書かれるべきは途方に暮れる新成人に救いの手を差しのべた人がいたことである。無関係な店がレンタルや着付けの協力を申し出て、大切な日を守ろうとしたのである▼助けられた新成人はその人の情を一生忘れまい。自分もそういう大人になりたいと思ったはずである。けっして誰かの晴れの日を傷つけるような大人ではなく。
ためしよみはお気軽にお問合せください0120-026-999営業時間 9:00~18:00 [祝日を除く平日]