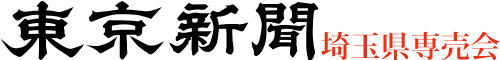福島県の郡山市にある高橋静恵さん(64)の家には、一本の梅の木があった。家族とともに成長し、春を呼んでくれるようにと、自宅の新築祝いに義父が植えてくれたのだ▼梅の木は、三人の子と同じようにすくすく育った。春の訪れを白い花と香りで告げ、初夏に実を付けた。親子で「梅仕事」に精を出して作った梅ジュースは、クーラーを使わない高橋家にとって、なくてはならぬ夏の清涼剤だった▼しかし、そんな家族の一員のような梅の木は、もうない。福島第一原発の事故の翌年もその翌年も、梅の実から放射性物質が検出されたため、庭の除染作業のときに伐採してもらったのだ▼梅の木がなくなった春を高橋さんは、こううたった。<どこを歩いても/濃淡の緑が爽やかだ…/だが、私の庭は/梅の木を切り株にしてしまったから/空は広くなったけれど/花の香りも若葉の輝きも失っている…>(詩集『梅の切り株』コールサック社)▼原発事故に奪われた当たり前の春の歓(よろこ)び。そうして、こう自問する。梅の木を切ったのは、原発に象徴される身の丈に合わぬ文明に身を委ね続けてきた、自分自身ではないのか、と▼詩は、こう続く。<私は梅の木を切ったのだ/いのちの連鎖を断ち切ったのだ…/ひとつのいのちを絶って/仕方がなかったと言えるのだろうか…>。八年目の春も、高橋さんはそう問い続けている。
ためしよみはお気軽にお問合せください0120-026-999営業時間 9:00~18:00 [祝日を除く平日]