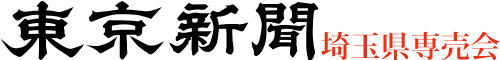鹿児島県の薩摩半島の南五十キロの海底に、とんでもない怪獣が潜んでいるという。その脅威は、ゴジラの比ではない。直径が十キロ余、高さ六百メートルという巨大な溶岩ドームだ▼このドームをつくっているのは、七千三百年前に噴火して、南九州の縄文文化を壊滅させたという鬼界カルデラ。今、もし九州でこの規模の巨大噴火が起きたら…という想定で書かれたのが、作家・石黒耀(あきら)さんが二〇〇二年に発表した小説『死都日本』だ▼霧島火山帯で巨大噴火が起き、火砕流は南九州をのみ込み、火山灰は西から東へと流れ、交通網や通信網など麻痺(まひ)させ、なすすべもないまま十万、百万の単位で人命が失われていく▼荒唐無稽な話ではない。現実に、破局的な大噴火の可能性を火山学者は「明日起きてもおかしくないが、予知は今は無理」と指摘している。では、どう備えるか▼四国の伊方原発をめぐる訴訟では広島高裁がその危険を認めて運転を差し止めさせた。だが、玄海原発をめぐる訴訟で佐賀地裁は、危険性は低いとの電力会社の主張を丸のみして再稼働を認めた▼『死都日本』には救いもある。政府が巨大噴火への最低限の備えとして、放射能汚染が救援や復興の妨げとならぬよう、火砕流にのまれそうな原発から燃料棒を運び出すのだ。大震災と原発事故を経験した今、そんな備えも考えぬことの方が荒唐無稽ではないのか。
ためしよみはお気軽にお問合せください0120-026-999営業時間 9:00~18:00 [祝日を除く平日]