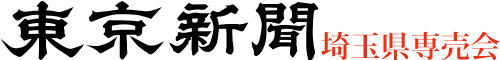<天井のあたりに音がしたと思つたとたんに、激しい揺れと家鳴り…そこいらじゆうが埃(ほこり)くさい空気になつた>。十九歳で関東大震災にあった作家幸田文は小説『きもの』で、その時を生々しく描いている▼町に火が上がる中、主人公は不安を感じながらも、家を離れ上野を目指す。火が迫りそうな場所や津波が怖い川沿いを避けての道中、見たのはわれ先に道を争ってパニックに陥った人々やなぜか火の手の方角に逃げる人々の姿だった▼死者や行方不明者は十万人以上で、逃げた場所で火に巻かれた人も多かった。そんな大震災の切迫感が伝わる。父の幸田露伴も随筆で無念を<人々は…自ら大なりとした其(その)大なることが、猛火の前の紙片よりもつまらぬ小なるものであることを悟らされた>(『震は亨(とお)る』)と表現した。災害多発の国で、経験が生かせず、犠牲を防げなかった無念だ▼大震災からきょうで九十五年。忘れたころどころか天災が忘れようもないほどの間でやってくるようになった。その中で迎える防災の日でもある▼西日本豪雨の被災者から「まさかこの場所が」の声も聞こえてきた。避難にさほど気を配ってこなかった反省が込められている。いつ、どこに、どう逃げるか。遅すぎず、パニックにも陥らずに▼九十五年前の課題と反省は、災害が絶え間なくやってくる今、よりはっきりと目の前にあるようだ。
ためしよみはお気軽にお問合せください0120-026-999営業時間 9:00~18:00 [祝日を除く平日]