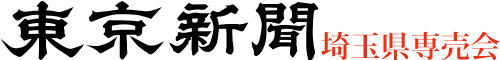時代小説の名手・葉室麟(はむろりん)さんの『秋月記(あきづきき)』で、江戸から故郷・秋月に戻った主人公は思わず「秋月はよいなあ」と、嘆声を漏らす▼<秋月では目をあげればすぐに青々とした山が見える。何ものかの懐に抱かれているような気がする>。緑の濃淡を重ねて連なる木々と山々と、そこから流れ出る豊かな川がもたらす安堵(あんど)の念。こんな俳句も生むような土地なのだ。<秋月は水よきところぬるみつつ>高浜年尾(たかはまとしお)▼だが、秋月がある福岡県朝倉市では、五日からの二十四時間で、五〇〇ミリ以上の雨が降った。十キロ四方の地に東京ドームならおよそ四十杯、ナゴヤドームなら三十杯もの水が一気に注がれ、いつもは優しく懐に抱いてくれる山が崩れ、水が牙をむいた▼九州豪雨の犠牲者は増え続け、安否が分からぬ人も多い。孤立し続ける人も数百人いるという。家が泥にのまれ、両親の行方が分からぬという男性は捜索を見つめつつ、こう漏らしたそうだ。「見つかってくれれば、今はそれだけでいい」。かけるべき言葉も、見つからない▼『秋月記』では、愛する人を突然失い、人知れず涙を流し続ける女性の心模様がこう描かれている。<それでも…どこまでも青々とした山並み、深い色をした空を見ていると、不思議に生きていく気力だけは湧いて来た…>▼せめて、そんな深い色をした空が、被災地の上に広がってはくれまいか。
ためしよみはお気軽にお問合せください0120-026-999営業時間 9:00~18:00 [祝日を除く平日]