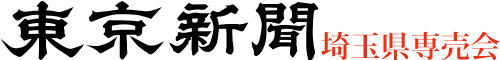町中の人たちが急に何かにとりつかれたように雪人間をこしらえるのに夢中になる。幻想的な作風で知られる米作家のスティーブン・ミルハウザーの短編小説「雪人間」(『イン・ザ・ペニー・アーケード』収録)はそんな不思議な話である▼最初は雪人間(日本の雪だるまのようなものか)だったのが、人々はどんどんと凝った雪像を作るようになっていく。雪のライオン、雪の噴水。雪の邸宅。やがて、その熱は冷める。雨が降る。雪人間たちは「すっかり溶けて変形してしまっていて、いまやただの雪のかたまりにすぎなかった」▼先週の大雪。まだ、しぶとく残る雪だるまを見かけ、その小説を思いだしたが、道に残った雪は硬く、滑りやすく、その上を歩くのはかなりやっかいである。何度も足をとられる▼住宅地を歩けば、一つの傾向に気づく。幼い子どもがいそうな新しい家の前には雪だるまがある。比較的古い家の前の道には雪がかなり残って凍結している。そんな気がする▼断っておくが、雪かき不足を非難するつもりはない。おそらくは、したくてもできなかったのではないか。たぶん住んでいらっしゃるのはお年を召した方だけでそれさえも重労働なのであろう。無論、空き家の前の道にも雪が残る▼雪だるまは少なく、硬く凍った道が続く。大雪の後に浮かぶ日本の今の姿なのか。なんだか、ひどく寒い。
ためしよみはお気軽にお問合せください0120-026-999営業時間 9:00~18:00 [祝日を除く平日]